|
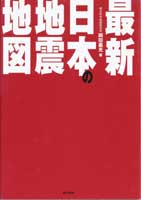
岡田光義 著 東京書籍1800円+税
地震があるといつも読み返してきた2004年に出された
優れ本の改訂版です。2006年発行。勉強になります。
宮城県沖は、1978年6月12日のM7.4の地震で当時62万人の仙台市が
近代化された都市で始めて襲われ注目された。
岩手福島を含めての死者28人、負傷者1325人。
ガス、水道、電気などのライフラインに重大な被害。
幸い津波は軽微。
2003年にも今回の地震津波で広く火災にあった気仙沼市近くでM7.1 死者0
2005年 宮城県南部地震 M7.2死者0緊急地震速報システムが始めて作動。
次の地震がいつ来ても不思議でなかった。
さらに日本海溝近くの三陸沖地震の発生確率を2012年までに30~40%と
警告されていた。 M8と計算されていたが
M9となる長い地震はさすがに想定外。
津波も、1896年明治三陸地震死者21,959人最高38.2mの津波が来襲。
1933年三陸地震28.7m。 死者は3,064人で、明治の津波を覚えていた人がいて、
その教訓が生きたとも。
有名な1960年のチリ地震津波死者122人。
高さは6mで、津波の怖さを再認識。
知っている人は知っていた地震・津波。繰り返される津波、
100年に1~2回は来るようです。
根本的に住み方を変えて、津波をやり過ごす
街づくりが必要。
新潟県知事泉田裕彦さんの
スーパー堤防で町を囲まない提案。
1段目 海岸部を、漁港や港湾、工場、公園、運動場などに。
2段目 高層住宅7階以上(ヘリポート付)公共機関、病院、大型商業施設。
津波の力を、上手く避ける建て方で。
3段目 20~40mの高地に個人の住宅や学校や療養施設など。
今回の津波でも大丈夫な高さで。避難所になる施設も津波に強い地域の
再建をしましょう。
美しい三陸の海岸を活かしながら、人や家が流されないで済む再建を。
ほとんどの家が流された町なら、自主再建をしだす前に、新しい町の夢を
語って区画整理の計画を立ててほしい。地方が、復興の希望デザインを建てる!
国は、迅速に金、人、物を集中させる。災害時の絶望感を取り除き共同体結成を。
当日 地震・津波災害から脱出。1~2週間 自主救援、耐乏避難所暮らし。
3週目 瓦礫の片付け、自立生活の模索。地震・津波からの避難。
命だけが助かったと言う人たち。火災や、津波警報が続いたために行方不明者の
救出が困難。津波がすべてのものを壊し、持ち去る力。なぎ倒された被災地が、
悲しい。阪神・淡路大震災の反省を生かしてほしい。
阪神では、大阪をはじめ、まわりの都市から続々と支援が入りボランティア活動も
活発だったが、東北は長い範囲で寸断孤立集落が多い。
いくら待ってもガソリンや物資が手に入りにくい。福島県の原発放射線事故が
追い討ちをかける異常事態。東日本地震・津波被害は、大変です。
『災害は進化する。』日本災害史;北原糸子編集(吉川弘文館)
被害を受けるものが増えているわけです。
本に災害は、日本の抱えている問題点をあらわにしてくる。時代の抱える
矛盾や不合理な状況を直視し、克服することが復興への道筋を付けることと
あります。中央集権国家では、表の見えるところに分権国家では裏の
見えないところにお金をかけると。復旧格差、復興格差を少なくせよ。
何よりも人間の心を癒す暖かいまなざしを忘れてはならないと。義援金は、
阪神では半年で1785億円集まり一世帯あたり40万円だったが生活支援に
どこまで寄与したかと。土木建築の被害は16~25兆円かかり、東北は阪神の
2倍以上かかると試算。自然災害が増えています。
万が一ではない東京直下型地震。災害の研究から対策・復興などすべてを
担当する災害省を作りましょう。10年待ってくれないかも?
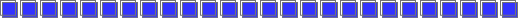
|